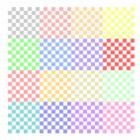hiroshi5 さんの感想・評価
4.3
物語 : 4.0
作画 : 4.5
声優 : 4.0
音楽 : 4.5
キャラ : 4.5
状態:観終わった
Kids on the slope complete review: jazz & jazz
◆作画
独特なタッチで昭和の雰囲気を上手く表現しています。はじめは馴染めないかもしれませんが、二話、三話と進むごとに違和感はなくなります。ジャズの演奏には特に力が入っていて、それはそれは躍動感溢れる作画でした。演奏自体、きっちり腕の動きや指の動きを再現していて、芸が細かいです。
◆音楽
ジャズを知ってる人なら誰でも一度は聴いたことがあるようなスタンダードナンバーが頻繁に使われています。個人的にはOSTを購入することをオススメします。ジャズとしてはイマイチかも知れませんが、本編の挿入歌としては最高でした。
◆キャラ
全てのキャラが均等に良い味を出してました。特に薫と千太郎のコンビは感情移入しやすかったですね。私が一番気に入ったのは薫です。薫ってひょろひょろってしてて弱そうなんですが、意志は強いし、恋愛沙汰には前向きで、非常に好感が持てました。
◆物語
恋愛と友情が本編の中心となっていまして、ジャズはそれを強調するためのものです。純粋な恋愛は心に響き、こちらもドキドキしてしまうと同時に凄い一つ一つの行動が理解できます。最後はちょっと焦った感が否めないですが、私としては別に問題はありませんでした。
***************************************
ここからはジャズの話をします。物語は恋愛中心なんですが、タイトルに使われているジャズのことや、挿入歌のことを知っておくと、この作品がより一層面白くなること必然です。演奏の仕方、そこに込められた意味。そういうものをちょっとでも深く理解でき
たらな~と思っています。
まずはジャズとは何か?からいきましょう。
◆ジャズについて
{netabare}
ジャズとはアフリカから奴隷としてアメリカに渡ってきた黒人が苦しみを和らげる為に弾いていた故郷の音楽が起源です。ジャズの根源が生まれ始めたのは1800年後半。ジャズがアメリカ全体に浸透したのは1900年代の初期です。
現在、ジャズには色々な種類があり、複雑さを増しています。
スウィングジャズ/ビバップ/ハードバップ/モダンジャズ/ファンキージャズ/フュージョンジャズ/ボサノバ/ラテンジャズ/フリージャズ/クールジャズ/スムーズジャズ/ファンクジャズなどなど。
言い方を変えればニューオーリンズ・ジャズ/ディキシーランド・ジャズなど色々名前が出てきたりします。まぁ名前なんかはあまり拘らなくても良いと思いますが、知ってたら面白いですよ。「あ、これはファンキーを取り入れているな」なんて発見していくのもジャズの面白さの一つです。
{/netabare}
◆ジャズの歴史
{netabare}
ジャズが音楽として生まれるには複数のステップがありました。その一つはラグタイム。ラグタイムとはジャズの原型の様な音楽です。この音楽はアフリカの民族音楽とアメリカに存在していた音楽とを融合させて生まれました。
当時、ラグタイムには楽譜が無く、今楽譜として存在するのは黒人達がプレイしていたラグタイムを白人音楽家達がノートにしたものです。
そのラグタイムが絶頂を迎えたのは1890年後半から1900年の初め。ラグタイムの主流の楽器は一台で複数の音を出せるピアノでした。当時、ピアノは現代で言う車やテレビのようなものでして、ピアノが社会的地位を表していたと言っても過言ではありません。この時期のピアノの売り上げはピアノが発明されてから現代に至るまでの期間で一番高いと言われているほどです。ピアノ自体にも大きな変化がありました。小さく、コンパクトな家
庭用ピアノ、アップライトピアノの性能が格段に上がったのです。それ故に、屋外でラグタイムが演奏された時は大人数のバンドでプレイされ、今のマーチングバンドと似ている形になっていました。音は単調なんですが、なんとも元気がでるようなメロディーでして、ラグタイムは聴いている人を元気にする、そんな音楽でした。
http://www.youtube.com/watch?v=O_dI6BZt06U
1920年に入って一つの大きな変化が生まれます。ルイ・アームストロングの登場と、少数でプレイできる音楽の出現です。
ルイ・アームストロングは真の天才でした。彼のハスキーな声、迫力のあるトランペットの音、そして何よりもトランペッターとしての技術。当時のトランペットは現代のトランペットとは違い、音が出にくく、また吹きにくかったとの話があります。それでもアームストロングの音色は凄かった。アームストロングの登場後、ヨーロッパとアメリカのあらゆるトランペッターが彼の真似をしようとして、その殆どが挫折したという逸話が有るほどです(笑)。彼はラジオ、テレビ、そして映画にまで出演し、ジャズという音楽を広めていきました。
そして、もう一つの変化がジャズそのもののカタチに変化が訪れたことです。ラグタイムを屋外で演奏する時はマーチングバンドのように複数の人間が必要になっていましたが、新しくルイやその当時のアーティストが提示していった音楽は個人でも演奏できるものでした。個々で演奏できる音楽、それは貧困層(黒人)をジャズに興味を持たせる大きな要因になりました。彼らは出稼ぎなどでお金を貯め、自分の好きな楽器を買い、道端などで必死に、自由気ままに演奏したのです。それが現代に続くジャズの起源です。
そして、ジャズの歴史上、いやアメリカの歴史としても捉えられる大きな出来事が1935年に起こります。
かの有名なベニー・グッドマンのビッグバンドが行った全米ツアーライブの最終日、カリフォルニアでのライブがジャズの歴史を一夜にして開幕させたのです。一般的なメディアがラジオだった当時、そのカリフォルニアのライブは全米放送されていました。彼が演奏した音楽は今までのジャズとは違い、ビッグバンド形成で鮮やかな音、そして何よりも躍動感溢れるリズムが特徴的でした。これがスウィングジャズです。
ベニー・グッドマンは天才的技術を持つクラリネット演奏者でしたが、人格破綻者としても知られていました。彼が最終的に注目するのは音楽だけだったからです。しかし、この音楽しか気にしないという彼の性格が彼の成功をさらに大きなものとしてのです。
単純に考えれば新しい音楽がラジオで流れただけでは全米で人気になる筈もありません。それは二つの大きな要因があったからです。
1、1930年はアメリカの大不況(The Great Depression)です。失業率、自殺率ともに過去最高を記録していたアメリカに元気のある音楽は元気のモトとなりました。
2、ベニー・グッドマンが白人だったことです。実はスウィングジャズというのは1920年代にフレッチャー・ヘンダーソンという黒人が完成させています。しかし、彼のバンドは全員黒人。大衆には受け入れられませんでした。
この二つの要因からベニーは見事の成功をおさめ、ジャズの黄金時代が始まるのです。
ジャズの黄金時代と聞けば、大抵の人は1950年代を思い浮かべるのですが、アメリカの全体に浸透していたという風に考えると1930年代になります。1950~1960年代はジャズの完成度で見れば黄金時代ですけどね。ちなみに、スウィングジャズの様にアメリカ全体で人気を得た音楽はロックやブルースがありますが、多分ジャズが一番初めだと思います。
1930年はビッグバンド支流でしたが、それ以降は小グループで演奏するようになり、ハードバップの流れを汲んだモダンジャズはジョン・コルトレーンの「至高の愛」(神との対話などといわれていますw)によって完成したと言われています。
1960年代以降は様々な形式のジャズが登場し、ジャズの可能性を広めていきつつも、かつての勢いを失い、1980年代にはかなり低迷します。最近では少ずつ人気を取り戻しつつあります。
{/netabare}
*************************************
曲ごとに説明していきます。
[Mornin'] Art Brakey
{netabare}
ブレイキーのジャズメッセンジャーズが結成してのは1955年、ブレイキーがホレスシルバーと共に共演してからです。その後何回かのメンバーチェンジが行われ、人気を低迷していった中、1957年のアートブレイキーの「ジャズメッセンジャー ウィズ セレニアスモンク」のアルバムが大ヒット。そして、1958年、ジャズメッセンジャーズの黄金期にこのアルバム、「モーニン」がレコードされました。メンバーは今までで一番充実した構成になっており、まさにオールスターと言っても過言ではないでしょう。(まぁ当時はモーガンとティモンズは若手でしたが・・・)
クリフォードブラウンが亡き後、マックスローチやソニーロリンズ、オスカーピーターソン、ジョンコルトレーン、キャノンボールアダレーなどの(何故かサックス奏者ばっかり挙げるのは自分がサックス好きだからですw)技術派プレイヤー達に期待が高まる中アートブレイキーは新しいジャンル、ファンキージャズを見事に確立し、その代表格奏者であるリーモーガンやボビーティモンズを取り入れた演奏を繰り広げました。
それが、モーニンです。
ちなみに、このレコードがベニーゴルソンを一躍有名にしたのも忘れてはいけません。特にBlues MarchとAlong Came Bettyの二曲がベニーゴルソンの本領が発揮された曲とも言えるでしょう。
それから、一つ注目したいのはドラムを演奏する川渕千太郎の演奏です。一話でいきなり躍動感のある演奏をやってくれましたが、あの演奏はかなりアートブレイキーを意識しているとしか言い様がありませんね.。
一見マックスローチのスピード感溢れる繊細なドラムさばきに見えますが(タムやスネアなど)、シンバルとバスドラムはブレイキーそのものでした。特にバスドラムの弾き方はアートブレイキーの真髄と言われるナイアガラ瀑布そのものです。
{/netabare}
[Bag's Groove] 2話のセッション
{netabare}
Miles Devis, Harold Mabern, Jackie MacLean, The modern Jazz Quartet, Thelonious MonkそしてOscar Petersonなどなど、色んなアーティストが演奏してきたスタンダードナンバーです。
物語では主人公である薫がコードをいきなり弾き始めていましたが(まぁジャズをかじっていれば誰でもできることです)、その後が厳しいのです。インプロバイズは音楽センスのある人間にとっては「あんなの思った旋律を適当に弾けば良いのさ」みたいな軽い感じで言われますが、音楽センスの無い人間には残念ながら練習あるのみと言った所でしょうかw
薫が即興に合わせられたということは、前者でしょう。つまり、絶対音感を持ち、その音をコードで表すことができる。しかも、粗方のコード進行も熟知している必要があります。
高度なセッションになればなるほど、必要とされる技術も高くなる。それがジャズです。
基本が即興なだけに才能が大きく現れる。それがジャズの良いところでもあり、悪いところでもありますね。
{/netabare}
[summertime] George Gershwin
{netabare}
この曲は有名すぎて逆に知らない人の方が少ないのではないかと思うくらいなんですが、誰が一番この曲を上手く弾いているかという疑問には答えられそうにないですね。そもそもジャズというのは、一番とかそういうのではなく、アーティストがどう感じたかを表現するだけですので。
だから、この曲をバラードで弾く人もいれば、アップテンポで弾くアーティストもいます。どちらが正解という訳でなく、どちらも正解です。要は、奏者の意図をちゃんと理解できるかがジャズを聴く上で重要になってくる訳です。
個人的には中でもHarold Mabern, Eddie Henderson, Artie Shaw, Stan Getz, Cheryl Bentyne, Charlie Parker, Art Pepperのが良かったです。
この曲が入っているアルバムを少し紹介しておきましょうか。
Harold Mabern [Falling in Love with Love]
Stan Getz [Getz Au Go Go Featuring Astrud Gilberto]
Charlie Parker [Charlie Parker with Strings]
Cheryl Bentyne [Sings Waltz for Debby]
どれを取っても十分楽しめると思いますがジャズを始めて聞く方にはHarold MabernかCheryl Bentyneをお勧めします。
そして、ボサノバが好きな方にはStan Getzを。
Tommy Flanagan - pianist
{netabare}
それから、本編で少し話があがっていたアーティスト、Tommy Flanaganにも触れておきましょうか。
彼は名脇役として活躍したピアニストです。軽く、またコロコロ転がるようなタッチはメンバー全体を輝かせる。しかし、それと同時に自分さえも輝かしくしてしまうのがフラナガンの特徴です。彼は1957年に[Overseas]という超有名アルバムを残しています(多分、Elvin Jonesの名前が挙がっていたことから、このアルバムの事を千太郎は言っていたのでしょう)。1957年と言えばフラナガンはJ.J.Johnsonのバンドメンバーとして活躍した頃で、彼の絶頂期(有名なのはSonny Rollinsの[Saxophone Colossus]でしょうね)。このアルバムは脇役としてで無く、ピアニストとしてフラナガンの才能を世に知らしめた内容になっており、ジャズ界に残る名盤です。そして、先ほど述べたElvin Jonesの才能を満喫できる内容でもあります。{/netabare}
{/netabare}
[someday my price will come] Bill Evans
{netabare}
アニメ内でもあったように、この曲が一番輝いていたのはBill EvansのPortrait In Jazzというアルバムでしょう。彼は他のアルバムやライブでこの曲を何回も弾き、素晴らしい演奏を残してきました。いつか王子様ががここまでビルエヴァンスの曲として取り上げられる理由には、彼の独特の奏法にあります。
1950年半ば、彼の人気がうなぎのぼりしていた頃、エヴァンストリオが「ベーズン・ストリート・イースト」というクラブで演奏していた時のこと、向かい側にあるクラブで演奏していたベニー・グッドマンに観客を全員とられてしまうといことが起きてしまい、エヴァンスを自信を無くしてしまいます。しかし、それが原因ですぐ後、新しいベーシスト、スコットラファロを相棒にすることが出来ました。そして彼はピアニストとしての黄金時代を築き上げる訳なんですが、ラファロとのタッグを組む過程で彼は今までジャズ界で一般化していたバッド・パウエルの流れを汲む一連のハード・バップ・ピアニスト達のノン・ペダル奏法と右手のメロディ・ラインの強調を一新しました。ペダル効果を再び採用し、トーンに色彩感と微妙な味わいを付け加え、さらに左右両手のバランスのとれた奏法を回復させ知的で思索的な香りを漂わせた、端端しい感性を感じさせる新鮮な魅力を生み出した訳です。
彼の生み出した奏法はいわゆる日本人向け、また「いつか王子様が」みたいなロマンチックな曲にはベストマッチしました。
実はビルエヴァンスは50~60年代を飾るピアニストだと認識されていますが、母国であるアメリカにはそこまで人気がありませんでした。彼が主に活動したのはヨーロッパです。
そして本編での演奏ですが、うん、音楽としては物足りなかったけど、物語を強調するには十分でした。特に途中で灰色の描写が投入されているのと、最後の顔が描かれているシーンは物凄く心に来るものがありました。うん、良かったな。
{/netabare}
[Blowin's The Blues Away]
{netabare}
この曲は四話から判る様にアップテンポでスウィンギーなファンキーの曲です。
多分有名どころは1959年のHorace Silverの「Blowin' The Blues Away」という曲名通りのアルバムでしょうね。
このアルバムのシルバーを聞いていれば判りますが、この曲で表現されている薫のピアノ奏法は実にシルバーのそれとリンクしています。
このアルバムではバッキングでの飛び跳ねるようなシルバーのタッチがフロント陣を煽り、熱気のあるスリリングかつ楽しげなソロの演奏に導いています。ファンキージャズファンには必見のアルバムでしょうね。
今回の演奏もそのシルバーの演奏を真似した結果だと思われます。気になった方は是非聞いてはいかがでしょうか?
このアルバムはシルバーの代表作であり、メンバーもブルー・ミッチェルやルイス・へイズを含める豪華なアーティストとなっており、全曲楽しめると思います^^
歌が好きな方にはDee Dee Bridgewaterが歌うBlowin' The Blues Awayをお勧めします。
アップテンポな雰囲気をビックバンドで表現しながら、聞き取れないぐらいの早口で歌う彼女はかなり魅力的です^^
{/netabare}
[But not for me] Chet Baker
{netabare}
このアルバムは今回でも一秒ぐらいワンシーンで出ましたが、Chet Bakerの「Chet Baker sings」というアルバムが代表的です。というより、Chet Bakerが歌うこの曲を越すアルバムは存在しないでしょうね。
この曲はいったい誰の、どんな、心境を歌った歌なのかについて意見が別れまして、結局私なりの考えでは「失恋した男の歌」でも「自分に振り向いてくれないちょっといじけた男の歌」でもどっちでも良いんじゃないかって感じです。
本当は女に向けた歌だ、なんて記述もありましたが、私としては男がしっくり来ます。
で、このチェット・ベイカーの曲がどう優れているかと申しますと、まず彼の歌声とトランペットの音色です。
彼の黄金期に収録されたこのアルバム(1954年)はベイカーの代表作と言われるジャズの名盤です。
彼が彗星のごとく西海岸に現れたのは1940年代後半。そこからジェリー・マリガンカルテットのメンバーとして参加、そして独立して1950年代後半までの活躍は目を見張るものがありました。
なんせダウンビート誌では53,54年の項目で、メトロノーム誌では54,55年の項目でかのマイルス・デイビスを抜いて人気投票トランペット部門一位に輝いていた程ですから。
そんな彼が武器としたのはルックスだけでなく、特徴的な中性的感覚の甘美しさとロマンチシズムを含めた哀愁漂う彼の演奏するメロディーです。
その特徴的なスタンスはどんなスタンダードナンバーをも彼風のアレンジに変えてしまい、観客を魅了してしまう訳です。
そんな彼の特徴を最大限に引き出したのが今作品という訳です。
私としてはジャズファンだけでなく、万人に聞いて欲しいアルバムですね。ちなみに、私はこのアルバムに収録されている「I Fall in Love Too Easily」、「Look for the Silver Lining」と「That Old Feeling」が一番好きです。
しかし、そんなベイカーも1950年代後半に入ると新たな風潮に付いていけなくなり、人気を失います。麻薬に溺れた後、投獄生活を何年も送り、復帰した1970年代初めも以前彼が持っていた雰囲気を削がれてしまい、人気が戻らずにジャズ人生に幕を降ろします。
やはり、彼の演奏は1940年から1950年初期に限ります。
{/netabare}
[Lullaby of Birdland] Chris Connor/Sarah Vaughan
{netabare}
そもそも、バードランドというのは、多分私の予想ですがNYCにあるBirdlandというジャズライブのことだと思われます。
Birdlandはジャズ界でももっとも有名なライブ場所であり、数多の有名なジャズアーティストが演奏してきました。
アルバムではJazz Messengersのライブが有名ではないでしょうか。
本編で出て来たLPはクリスコナーの「バードランドの子守唄」。これは1953年にレコードされた有名なカイ・ウィンディングらとのセッションで、それはそれは良い雰囲気に仕上がっています。
クリスコナーはアニタ・オデイ、ジェーン・クリスティと共に、ケントン楽団出身の三大白人モダン・ジャズ歌手と呼ばれていて、独特なハスキー・ヴォイスを使いジャズ界で輝いていました。
ジェーン・クリスティの可愛さを漂わせたウェットなハスキーとは違い、どこか開き直ったドライなハスキー声を持ち、天性の豊かな音量で歌い続けました。
噂では、クリスコナーはレズだったそうですが、それもなんとなく頷けますね。
で、今回の曲、「バードランドの子守唄」はクリスコナーの代表作である訳なんですが、これは決してクリスコーナーの歌うバードランドの子守唄が一番言い訳ではありません(個人的意見ですが)。
「バードランドの子守唄」とジャズファンが聞けば一番に思いつくのはサラ・ヴォーンの「Sarah Vaughan with Clifford Brown」でしょうね。
サラ・ヴォーンは好き嫌いで結構意見が別れますが、文句なしのジャズ界トップのシンガーでしょう。
彼女の天才的技術と生まれ持った才能は他のどのシンガーをも圧倒します。エラやビリー・ホリデーなどの有名シンガーと良く比べられたりしますが、私はサラが一番だと信じて疑いませんね。
サラの力の源は生まれ育った環境にあります。1942年10月のある水曜日、当時十八だった彼女はハーレムにあるアポロ劇場における有名なウェンズデイ・アマチュア・ナイト・コンテストで優勝します。その報酬として与えられた一週間のアポロ劇場出演中、それを聴いたビリー・エクスタインが友人であるアール・ハインズに推薦し、11月からハインズ楽団のセカンド・ピアニストとして活躍するようになりました。
その楽団メンバーの中に在籍していたのがモダンジャズの開拓者であるディジー・ガレスピーやチャーリー・パーカーらであり、サラは彼らから強い影響を受けました。
彼女はエクスタインからモダンな唱法を学び、パーカーやディジーからバップの何たるかを教わりました。
そして、彼女は自然にオフキーで歌い始め、バップのビートやコード、そしてバップフレーズなど複雑で高度な技巧を習得していったのです。
長くなりましたが、これが、サラは他のどのジャズシンガーよりも上手いとされる所以です。ビリー・ホリデーは環境に恵まれず、エラは天才的技術を持ちながらも、少し生まれてくる時代が早かった。ここがサラと他のアーティストとの違いです。
そもそも、サラの音域と音量、そしてバップ・スキャットなどの技術は他のどのシンガーよりも優れているし、唯一対抗できるであろう、エラは、前述した通り、少し環境が違いました。
で、本題に戻りましょう。
その天才歌手サラが歌った「バードランドの子守唄」はなんとも言葉では表しがたい、本当に素晴らしい完成度になっています。
これはジャズファンでなくとも、是非聴いていただきたい。
メンバーがこの頃のオールスターに近い状態で、サラも絶頂期。これで良いレコードが録音されない訳が無いと思いますが、当時のジャズファンもここまで良いアルバムができるとは思っていなかったのでないでしょうか。
注目すべきはトランペットを含めるホーン奏者とサラのスキャットのやり取り。これが本当に素晴らしい。
ちなみに、このレコードは全曲聴き応えがありますが、私は「April in Paris」「It's Crazy」「He's My Guy」も好きです^^
{/netabare}
[You Don't Know What Love Is] Sonny Rollins
{netabare}
ジャズのスローバラードのスタンダードナンバーです。
さて、この曲で誰が有名かと言われると、ぱっと思いつくのはソニー・ロリンズ、ビリー・ホリデー、それからチェット・ベイカーあたりですかね。
特に有名なのはソニー・ロリンズの代表作でありジャズ界の傑作と言われる「Saxophone Colossus」に収録されている「You Don't Know What Love Is」(ちなみに、このアルバムは一話で薫がムカエレコードに入ったシーンのバックに飾ってありました)。
ソニー・ロリンズのこのアルバムがここまで有名な理由は、単純な話、ロリンズの実力が十二分に発揮されたレコードだからだと思われます。
そもそも、ロリンズには”ロリンズ節”という言葉があるように豪快なトーン、縦横無尽に澱みなく続くフレーズが特徴的です。
さらに、彼の人生にも映し出されているように、意外にも繊細な一面が彼の音楽を引き立てているのでしょう。
彼は49年にバブズ・ゴンザレスのバンドで初録音した後、マイルス・デイヴィスに認められ活動を共に。その後技術に磨きをかけていき、1954年のデイヴィスのアルバムで自己のオリジナルである「オレオ」「ドキシー」「エアジン」といった代表作を作曲することで頭角を現し始めました。
その後麻薬癖を直すために雲隠れした彼を拾ったのはかの有名なクリフォード・ブラウン&マックス・ローチのバンド。55年からは独立もし、「ワークタイム」というアルバムも出しました。
その翌年に出したのが、この「サックスフォン・コロッサス」。
このアルバムを経て、彼の名前は不動のものとなる訳です。
ちなみに、彼は現在も活動中であり、2006年にジャズ界の巨匠であるオスカー・ピーターソンが亡くなられてからは、モダンジャズ界最後の巨匠であることは間違いないでしょう。
ある、ジャズ評論家はソニー・ロリンズをこのように評価しています。
「細かいことに拘らないおおらかさ、それでいてすべてを包み込んでしまう包容力の大きさがあるのだ。それになんといってもあの歌心の豊かさ、ぐいぐいと引きずりこんでしまうような懐かしくも親しみに満ちたメロディックな味わいは、聴き手の心を捉えて離さない。とりわけ50年代半ばにおけるロリンズは、奔放にして大胆な、かつおおらかでスケールの大きいアドリブ、それにサウンド一つとっても真の迫力を盛ったガッツ溢れた男性的トーンなのである。あの重量感、あの圧倒感、あの厚み、あの風格、あの熱気、そういった中にも独特の軽妙酒脱な開放感とユーモラスな味が溢れ、緊張感の中に、寛ぎを与えているのだ。そのアドリブは簡潔さと複雑さ、緊張と弛緩を巧みに配置し、均等のとれたフレーズと不均等な音のなぐり描きが絶妙なバランスを生み出し、独特の構成美を作っているのである。まさにそれはジャズ史上におけるアドリブ芸術の頂点を築きあげたものと言って良いであろう。」
まぁ~べた褒めですねw
しかし、この評論家が書いていることは間違いではなく、事実だと思われます。
で、話を戻しますと、ここまで評価の高いアーティストの絶頂期であるアルバムが「Saxophone Colossus」であるということです。
このアルバムには他にも何曲は収録されていて、どれを聞いても絶品。まさに、至高のアルバムといって良いでしょう。
「You Don't Know What Love Is」に話をさらに戻しますと、他にも色々なアーティストが弾いていますが、私はEddie Higginsが弾くこの曲が大好きです^^(←またおっさんじみたことを言ってしまった汗)
{/netabare}
[now's the time]
{netabare}
訳せば、「今がその時」。まさにこの七話を表現するに相応しい選曲。
これも言わばスタンダードナンバーでして、アートブレイキー、チャーリー・パーカー、オスカー・ピーターソン、ジェイ・ジェイ・ジョンソン、マイルス・デイヴィスなど有名なアーティストが好んで演奏しています。
タイトルからも判るように、ライブで演奏されることが多いようですね。
個人的にはアート・ブレイキーの「A Night at Birdland」に収録されている「now's the time」が好きです^^
あと、ソニー・ロリンズのアルバムで「Now's the time」というのがあるんですが(曲とは関係ありません)、このアルバムも必見ですよ~。
{/netabare}
[my favorite things] John Coltrane
{netabare}
で、次にmy favorite thingsですが、これは言わずもがな、John Coltraneが演奏したものが一番有名でしょう。
今回の七話でコルトレーンが死んだというセリフがあったので多分アニメの時代設定は1967年7月17日なんでしょう。
1967年。それ程にコルトレーンの寿命は短かった。産まれたのは1923年ですから44歳。その短い人生の間に彼はジャズという音楽を完成させてしまった。
多くのジャズ評論家はコルトレーンは苦しむ為に生まれてきたのではないか、ということを言ったりします。
それ程に彼は常に先頭だった。
1950年代の初め、彼がまだまだ無名だったころ、ソニーロリンズがサックス界を統治していました。全てのサックスフォンニストがロリンズをコピーしました。そんな中、デイヴィスグループに新しいサックス奏者を迎えることになり、当然のごとくロリンズを呼んだところ、ロリンズはこれを断りました。
そして、ドラムのフィリー・ジョーンズがコルトレーンを推薦したのです。これがきっかけで、コルトレーンは彗星のごとくジャズ界のスターとなったわけです。
デイヴィスや他のアーティストから影響を受け、独自の音楽を作り出し、それまでロリンズ一色だったサックスフォニストたちは宗教の衣替えを初め、コルトレーンの演奏をコピーするようになります。
コルトレーンは画してジャズサックス界の帝王となる訳なんですが、トップに立ったコルトレーンは求める音楽が判らなくなった。
トップである為常に進歩しなければいけないが、どれを基に進歩させれば良いのか判らない。
その苦渋を味わい始めたのが1960年代の初めです。ロリンズという競争相手は麻薬をやめる為二度目の雲隠れをし、他の演奏者は全員コルトレーンを見習っている。
そこからのコルトレーンは音楽に飢えた猛獣にようでした。自分の進歩に使える未知の音楽を探求するため、様々の音楽を聴いていき(スペイン、アフリカ、インドなど)、それを己のジャズにコンバートしていったのです。
そして、完成したのが1964年に収録した「至上の愛」です。一般的には神との対話と呼ばれるこの曲は4パートからなっており、一曲一曲が長い。そして常人が理解できる音楽ではありません。
ジャズは必ずと言っていいほどカバー曲が他のアーティストによって演奏されるのですが、この曲のカバーだけは誰もやっていませんね。多分、これからも永遠にカバーされることはないでしょう。
それだけに、この曲は「完成」しているのです。
しかし、我々常人には聴いたところで理解できるわけも無く、面白くもなんともありません。
やはり、コルトレーンはロリンズと張り合っていた1950年代後半から、テナーのマウスピースが不調でソプラノで演奏していた1960年代初期が一番お勧めですね。
my favorite thingは1960年に収録された音楽で、これまた有名な逸話があります。
この演奏でドラムをやっていたエルヴィン・ジョーンズが話していたことなんですが、このアルバムを収録するのにmy favorite thingsを9回も連続で演奏し直した、というのです。
エルヴィンはこの9回の演奏を「本当に素晴らしかった。9回も同じ曲を演奏していたのにまったく飽きなかった。毎回違う曲を演奏しているようだったよ」みたいなことを(ビデオで見たのできっちり覚えていません汗)言っていました。
それだけに、コルトレーンのこの曲に対する思いいれと完成に対する執着があったのでしょう。
実はこの頃から彼の悲壮は始まっていて、この演奏は彼の悲痛をそのまま音楽に出したような演奏になっています。
それだけに、心に響くものがあるのかもしれませんね。
他のアーティストでもこの曲を上手く演奏しているのは沢山いますが、個人的にはジョニー・ハートマン、サイラス・チェスナットが好きです。
話は変わりますが、OSTのアルバム聞いてた時から気になっていたことを・・・。
薫のmy favorite thingsが誰かの演奏に似てるな~って。
先週聞いたときには分からなかったんですが、ふとあるピアニストの演奏を聴いて、分かりました。
McCoy Tynerです。マッコイ・タイナーこそ、今回の薫の演奏のベースとなった演奏者で間違いないでしょう。
彼は16歳の時、かのバッド・パウエルを師匠としてからジャズに磨きをかけ、マイルス・デイヴィス、ビル・エヴァンス、そしてジョン・コルトレーンから強い影響を受けました。
ジョン・コルトレーンが収録した「My favorite things」のピアニストもマッコイ・タイナーです。
じゃ、なんでコルトレーンの曲聴いたときに分からなかったんだ?って話ですよね・・・。これは自分でもちょっと分かりませんw
でも、個人的には薫のピアノ演奏のベースを知りたいならマッコイ・タイナーのソロを聴くことをオススメします^^
{/netabare}
[these foolish things]
{netabare}
後悔の念や今は過去の輝かしい記憶・・・。複雑で頭を悩ませた出来事、ちょっとした些細な恋心・・・。
そういった曲に含まれている繊細かつノスタルジックな雰囲気を非常に上手くこの第八話内に取り入れてましたね。
タイトル選びは毎回最高級ですねw
で、この「these foolish things」はまたまたジャズの有名スタンダードナンバーな訳でして、この曲を演奏してきたアーティストも星の数ほどいます。
個人的にはBeegie Adairの「I'll take romance」に収録されているこの曲が一番のお気に入りです^^
有名なので言えば、Clifford Brownの「More study in Brown」に収録されているのとか、Billie Holidayの「These foolish things (remind me of you)」があると思います。
特にビリー・ホリデーが歌うこの曲は本当に感情が篭っていて圧巻です。
ビリー・ホリデーは本当に恵まれていなかった女性であり(黒人であった為)、彼女が歌う曲は黒人差別を非難するものが多いです。
黒人ゆえの貧しさから小学校にも満足に行けなかった彼女は10歳で強姦され、不良少女として感化院送りになった。出所後は女中奉公から娼婦にまで身を落とし、売春罪で刑務所暮らしをするなどして10代後半にして人間が味わう悲劇という悲劇を体感しました。
歌手として成功してからも、彼女は差別を受け続け(夫との問題もあった)、結果麻薬に走り裁判や投獄などを何度も経験したということです。
彼女への差別は死ぬ間際まで続いたそうです。本当に死ぬ間際、救急車で病院に運ばれた彼女は黒人の麻薬患者として瀕死の状態のまま放置され、死の床についてからも官憲の監視下に置かれていました。
そんな混沌の中で彼女自身を生かしていたのは歌の力でしょう。彼女の独特なハスキーボイスと天性の歌手としての才能が彼女の苦痛を和らげてくれたのではないでしょうか。
それは晩年の彼女が酒とたばこと麻薬の性で声を殆ど失った後でも、心の底から込み上げてくる叫び声のような歌声で歌っていた時にも同じ事が言えます。
彼女の歌は心に響くものがある。だからこそ、ジャズ・ヴォーカルの女王として約20年ものの間君臨することができたのでしょう。
そんな苦痛まみれの彼女が歌う「these foolish things」は本当に心に響くものがあって、グッと来ます。
是非、聴いてみてください^^
{/netabare}
[Love me or leave me] Ruth Etting
{netabare}
映画のタイトルにもなったこの曲はWalter Donaldsonが作曲し、Gus Kahnが作詞したんですが、実際に有名になった経緯にはRuth Ettingが欠かせません。彼がかの有名なブロードウェイでこの音楽を流した事からこの曲はジャズのスタンダードナンバーとなったわけです。
この曲を録音した有名なアーティストは数知れませんが、個人的にはAnita O'Dayの歌うバージョンが好きです^^
タイトル通り、なんというかすっぱりした感じが良く出ていて、非常に良いです。
ちなみに、この曲のタイトルを使った映画はRuth Ettingの物語をベースとした一種のドキュメンタリー作品となっています。興味のある方は是非見てください^^
{/netabare}
[In a sentimental mood] Duke Ellington
{netabare}
デューク・エリントンが作曲した超有名曲です。有名なアルバムはジョン・コルトレーンと共演した「Duke Ellington & John Coltrane」。このアルバムに収録されているこの曲はまさにセンチメンタルムード。当時、ジョン・コルトレーンのテナーサックスのマウスピースが故障していたことからアルトサックスが使用されているのですが、これがまた、人を感傷的にさせる。思わず涙が流れるようなそんな「寂しさ」が入り込んだデキになっています。
他にもビル・エヴァンス、アート・テイタム、ソニー・ロリンズなどがこの曲を深く、深く演奏しています。中でもビル・エヴァンス「California Here I Come」では特徴的で、悲しい雰囲気で弾くのかと思いきや以外に明るいキーを使っての演奏。また、アート・テイタム「The Complete Pablo Group Masterpieces Disc 2」では感傷的な雰囲気を醸し出しながらも相変わらずの天才的テクニックで観客を圧倒させます。
この曲を通す事で、デューク・エリントンがなぜここまで人気なのかが少しは理解できるのではないでしょうか。彼の作曲する曲は独特な旋律を保ちながらも心に訴えるものがある。しかも、ジャズアーティストはそれを自分なりにアレンジして演奏する。
やはり、ここがジャズの醍醐味ではないでしょうか?
{/netabare}
[left alone] Malcolm(Mal) Waldron
{netabare}
この曲を言えば、まず出てくるのはマル・ウォルドロンでしょう。彼の1960年に収録した「left alone」というアルバムは超有名で、このアルバム以外ではあまり知られていないぐらいです。
この「left alone」という彼のアルバムは1959年に死去した親愛なるビリー・ホリデーに捧げたもので、それはそれは暗いものとなっています。
ウォルドロンはビリー・ホリデーから強い影響を受け、さらに最小限の音で自分の思いを表現するセレニアス・モンクの奏法にも影響を受けていました。そのせいか、彼の求める音楽は常に暗く、「孤独感」が滲み出るような音楽ばかりになっています。
明るい音楽が求められたアメリカでは、案の定、まったく人気を得られなかったのですが、日本やヨーロッパでは「left alone」を通して話題になりました。そういう意味ではビル・エヴァンスと共通する点はあるかもしれませんね。
{/netabare}
[all blues] Miles Davis
{netabare}
マイルス・デイヴィスが作曲したこの曲は「Kind of Blue」に収録されています。全体的に7thコードで作られているこの曲は独特なコード進行になっており、当時にジャズミュージシャンを驚かせました。
静かなバックから何かオドロオドロしいものが出てくるかのような始まりから、線の細いマイルス・デイヴィスのトランペットが流れてくる。それだけで、もう彼の世界観に引きずりこまれます。その後も同じテンポでグループ全体でデイヴィスの音楽を表現していく。
聴いていて、違和感なく、その世界に浸透していくのが彼の音楽の特徴です。
{/netabare}
色々大量に書いてきましたが、以上のようにジャズというのは非常に複雑な音楽です。その片鱗を理解しながらこの作品を見ることで、物語に対する観方が良い方向に変わればなと思っています。個人的には制作側のタイトル選びに高い評価を下したいところです^^