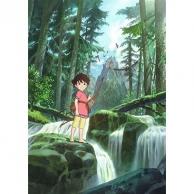renton000 さんの感想・評価
4.8
細田監督の良さがふんだんに!(補足追記)
あらすじは他の方のレビュー等をご参照ください。
2回目でした。2時間くらいの現代ファンタジー。
1回目は、ながら見だったせいもあってか、あまりよくない印象を持っていたと記憶しています。今回きちんと見て、この作品の魅力にやっと気付けました。好きかどうかは意見が分かれる可能性がありますが、表現が非常に細かく、圧倒的な情報量が込められた傑作だと思います。私は非常に楽しめました。(補足を追記しました)
伝聞形式:{netabare}
この作品は、オープニングでもエンディングでも、語っていたのはユキでしたよね。つまり、この物語は、語り手のユキの視点で描かれたものだったと言えます。この作品を、第三者の視点で描かれた家族の「ドキュメンタリー」として見てはいけませんでした。あくまでも、ハナから伝え聞いた話にユキ自身の体験を盛り込んだ、ユキの「思い出」のストーリーとして見る必要がありました。
この辺を誤解するとやや説明不足に感じるかもしれませんね。この作品の世界が、ユキの中で再構成されたものであることを理解した上で視聴する必要がありました。
オオカミ男がどのような生活をしていたのか、なぜ受講していたのか、なぜ死んでしまったのか。これらが不明なのは、第三者による俯瞰の視点がないからです。
アメについてももちろん同様です。アメの単独シーンではセリフがありませんでした。すぐ話せるところにハナやユキがいないとアメのセリフは分からない、ということです。
ニラサキのおじいさんの隠された思いも、嵐の日になぜユキとソウヘイだけが置いて行かれたのかも、ハナやユキがいないから不明である、というだけでした。
ユキとハナの二人が知らない事柄や、ユキがハナから聞いていない事柄は、ユキの「思い出」の中では語りようもなかった、ということですね。説明に不足しているのではなく、伝聞形式を採用しているために説明ができなかったのです。
{/netabare}
ハナとユキの母親像:{netabare}
まず、ハナにとっての母親とは何なのかを探ってみます。
ハナが父親と写っている写真が出てきますが、その写真にハナの母親は写っていませんよね。写真のハナはかなり幼いですから、物心がつく前に母親を亡くしている(又は離婚している)可能性が高いです。社会から隔離されたオオカミ男と両親を失った孤独なハナが恋に落ち、家族(子供)を求めたのは何ら不思議なことではありませんでした。
ハナはオオカミの育て方について「知らない」と言っていますが、母親による人間の子供の育て方も把握していなかったのです。親はみんな子育ての素人だという概念以前の問題で、母親という存在を知らないんです。
では、ユキにとっての母親像とは何なのか。
ハナは「辛い時でも笑っていれば乗り越えられる」を信条としています。また、ユキの誕生に際して「辛い思いをしないで元気に育ってほしい」と願っています。
このことから、ハナはユキに対して、自分の辛さを一切伝えずに、笑顔であったことを伝え続けたのだと思われます。これがユキにとっての母親像を「強く優しい笑顔の母」に固定化しているというのは否定できないところでしょう。ただ、それが悪い方へ傾いているのではなく、ハナとユキの間にある愛情についての表現だったと言えます。ユキがそこに疑いを持たないために、あたかも理想像のように見えるのです。
母親を知らないハナと母親を理想的に見るユキですから、この作品には現実的な母親と言うのは事実上存在しないことが分かります。そして、私たちはユキの「思い出」に影響され、ハナに対しては「強く優しい笑顔の母」というイメージを持ってしまいます。ただし、実際にハナがそのように描かれているかというと必ずしもそうでもありませんよね。
例えば、子育て中のアパートでは、部屋は汚れ、ポストは郵便物であふれています。本に頼る姿も頻繁に出てきますが、結局のところ、ハナを救っていたのは本ではなく、周りの人々です。子供の親離れにも気付いていませんでした。ハナのイメージは「強く優しい笑顔の母」なのですが、周辺の描写を踏まえると一般的な母親と同様に弱さを見せていました。
子育てに苦労するシーンでは、ツバメやクマが子連れで登場しています。動物との対比でも苦労を垣間見ることができました。本に頼る描写は後半ではありませんし、理想像のように見えるハナ自身も成長していたのです。
ちなみに、花はハナの精神状態のバロメーターでもあったようです。分かりやすいのは花瓶で、オオカミ男が亡くなった直後やアパートでの育児中は、部屋に飾る花瓶の花は減っていました。花壇が充実している描写もかなり後半にならないと出てきません。
笑顔以外のハナを知るには、周囲の描写に注視する必要がありました。
{/netabare}
ユキと二面性:{netabare}
ユキとアメは、人間とオオカミの選択という作品のメインテーマを背負っています。家の前の分かれ道も、小児科と動物病院も、左が人間で右がオオカミとして描かれていました。ユキとアメが並んで立つシーンも、ハナによる手書きのユキとアメも、左がユキで右がアメと統一されていたようです。常に左側が人間で右側がオオカミだという、方向性の統一が描かれ続けていました。
ユキを知るためには、この左右の選択に、鏡を加えなければなりません。どこかのレビューで書いたのですが、鏡や水面などの姿が写るものは、二面性の象徴として使われます。
ソウヘイとのトラブルの前、鏡の前で口論が行われます。
この時のユキは、現実のユキと鏡に写ったユキの両方が描かれています。そして、左側の階段を下りて、一旦右に振れるも、すぐさま左にはけて行きます。人間とオオカミ(左と右)に揺れているユキが、人間(左)側に行きたいという描写です。二面性を象徴する鏡と、左右のどちらからでも降りられる階段という舞台、そしてハナから聞いた人間でいるためのおまじないを使って、人間とオオカミに揺れるユキの心情と人間側への希望を強く描いていました。
その時のソウヘイは階段の右側を下りますが、下りきることはありません。その後に「一匹狼」を自称するとしても、下りきれないのは当然のことです。
一方で、嵐の夜の鏡の前では、ユキは鏡に映った姿しか描かれていません。アメとのケンカに負けた後ですし、それ以外でオオカミの姿にはなっていませんので、鏡の前だとしても二面性を描く必要がなくなっていたのです。人間であることへの強い意志を感じ取ることができます。
このときのユキのセリフは「大人になりたい」です。このセリフは思春期に入った子供の特典のようなものです。オオカミの成長スピードならこの段階で大人になることも考えられますが、人間であることが確定したユキがこの段階で大人になることはあり得ませんので、あくまでも人間の思春期の真っ只中として描かれていました。なお、思春期への入りの描写は「匂い」(※)でした。
なお、最後に二面性が描かれる人物は、ユキでもアメでもなく、ハナでした。アメを見送った後の水たまりに写る二人のハナです。かなりくっきりと写っています。人間とオオカミを独り立ちさせたというハナだけのエンディングです。最後に「大丈夫」と言われるのも、ユキやアメではなく、ハナでした。
{/netabare}
上記以外にも、重要なシーンに合わせるような瞳の揺らぎや光の描写、動物の姿など画面の隅までまで見どころがたくさんありました。家の修繕を進めていくうちに、細部の美しさに気付いていく描写は、家の柱を介して子育てにリンクされるなど、素敵な表現だったと思います。時をかける少女やサマーウォーズと同様に、人間を肯定的に捉える細田監督の特徴は出ていたと思います。
対象年齢等:
10代くらいから見ても大丈夫だと思います。性に関する描写も10代なら問題ない程度のものです。宮崎駿作品のように、見るたびに理解を深めていける作品だと思いますので、長い期間を通じて楽しんでいきたいですね。
(※)「匂い」の補足{netabare}
ソウヘイはユキに「獣臭い」と言っています。なぜこの「匂い」がユキの思春期入りの描写になるのかについて、補足を入れておきます。
このセリフは、表面的には「オオカミ臭い」という意味を持っています。これがユキの受け止め方であり、その後のストーリー展開に直接的な影響を及ぼします。ただ、描写的には、全く別の意味を持つことが分かるようになっていました。
単に「オオカミ臭い」ことを表現するのならば、この「匂い」は、オオカミが気付かずに人間が気付くものでなければなりません。すなわち、ユキ以外の生徒たち全員が気付く「種族の匂い」のはずです。しかし、ソウヘイ以外の女子生徒たちは、その「獣臭い」には気付いておらず、気付いていたのはソウヘイだけでした。
つまり、実際の「獣臭い」は、人間かオオカミかを判別する「種族の匂い」ではなかったということです。女子生徒が気付かずにソウヘイだけが気付くという、女性と男性を判別する「性別の匂い」だったのです。端的に言うと、「生理の匂い」「血の匂い」という意味でした。これをソウヘイは「獣臭い」と表現していたのです。
初見時には、ソウヘイの臭覚や感性が他の人より鋭くて、「種族の匂い」に気付けたのでは?と思ってしまったのですが、そう言い切ることはできませんよね。ソウヘイに関して、そのような描写・エピソードは用意されていませんから。その結論を出してしまうと、先入観や思い込みで解釈をしていることになってしまいます。
このシーンでは、ユキに女子生徒と男子生徒を絡ませることで、<オオカミのユキ⇔人間の女子生徒&ソウヘイ>という対比に基づいた「種族の匂い」ではなく、<女性のユキ&女子生徒⇔男性のソウヘイ>という対比に基づいた「性別の匂い」を演出していたということしか見えてきませんでした。
したがって、このときのユキは、ユニセックスな子供時代を終え、男性が意識する女性へと変わっていたということになります。それゆえに、「匂い」でユキの思春期入りが描かれていた、と言えるのです。ユキの内面からではなく、他者の視点からこれを見せていました。ユキは、オオカミの血にコンプレックスを持っていますから、過敏に反応し過ぎて誤解をしてしまった、とも言えますね。ユキの内面的な思春期は、そのあとの描写で描かれていました。
{/netabare}