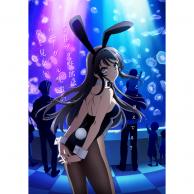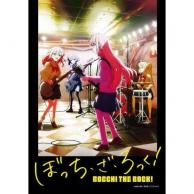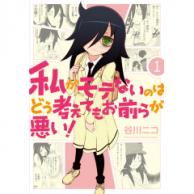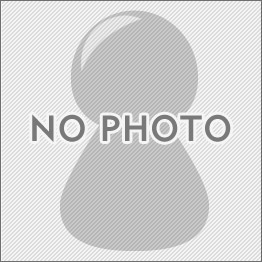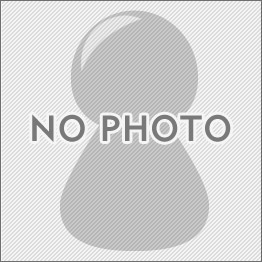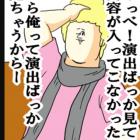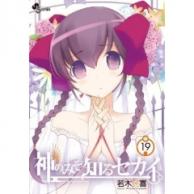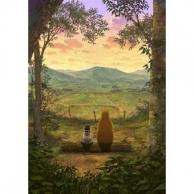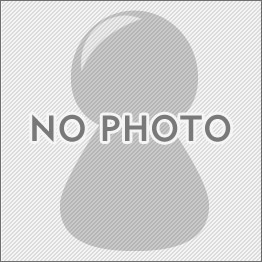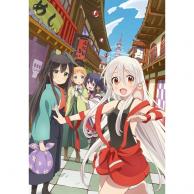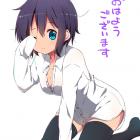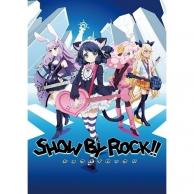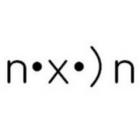けみかけ さんの感想・評価
5.0
なるほど、酷評をする人はコレがパクリに見えるわけですね、その価値観を変えるのは出来んのでしょうが、コレがゼロ年代ヲタク文学への愛のあるアンサーであることは明白!
『さくら荘のペットな彼女』を手掛けた鴨志田一先生と溝口ケージ先生が再タッグを組んだライトノベルが原作の全13話のSF、略称は『青ブタ』
『さくら荘』が学園青春ラブコメだったのに対し、長く続いた『さくら荘』でファンの年齢層も上がったことだろうということで、お二人は担当編集の反対意見を押し切り(笑)意図的にターゲット年齢層高めのSF作品にすることで切り返しを計っています
制作はA-1高円寺ことCloverWorks
監督は増井壮一で構成と脚本は横谷昌宏ということで奇しくも“さくら”繋がりの『サクラクエスト』コンビが手掛けました
梓川咲太(あずさがわさくた)はニヒルな高校2年生
梓川サービスエリアの梓川に、花咲く太郎の咲太で梓川咲太
彼はある日の休日、野生のバニーガールに遭遇する
その正体はかつて国民的人気を誇った芸能人で今は休業中の同じ高校に通う3年生、桜島麻衣(さくらじままい)
彼女は有名人でありながら他人から存在を全く認知されなくなった“思春期症候群”と言われる不可思議な都市伝説に巻き込まれているという
思春期症候群に遭遇した経験を持つ咲太は麻衣先輩から「忘れなさい」と忠告を受けるも麻衣先輩が美女であることを含め放っておけず、思春期症候群の世界に首を突っ込み始める
やがて咲太のざっくばらんな性格や隠されていた誠実さに麻衣先輩も心を開き始める…
主人公の咲太を取り巻く6人の美少女と彼女達の身に起きる不可思議現象を紐解いていく青春SFストーリー
今作、正直2018年のテレビアニメの【最高傑作】と言って過言では無いでしょう
放送当時、あまりにも仕事が忙しくて視聴をかまけていたのですが、ラジオ番組でライターの前田久さんが紹介されてるのを機に、完結篇になる劇場版ももうじき公開されることだし、ってことで一念発起して半年遅れでイッキ観してみました
いや、本当に面白い
なんでもっと早く教えてくれなかったんだよ!w
何話が面白いとかじゃなく、全話捨てるとこ無し!
そもそもよく原作をここまで短く纏めることが出来たと思います
横谷さんの一人脚本すっご
あにこれでも2019年4月現在、放送時期ランキングでアレほど話題を集めた『SSSS.GRIDMAN』や『ゾンビランドサガ』や『若おかみは小学生』を抑えてベスト1に輝いています
こーゆー名作をちゃんと評価する辺りが、オイラがあにこれの皆さんを信頼する理由ですねぇ
しかもその内訳が「大絶賛」してる人と「大酷評」してる人に真っ二つに別れているwww
その上での1位って王道中の王道じゃないですかw
『エヴァンゲリオン』かってのw
まずアニメやラノベに詳しい人ほどこの作品に漂う既視感に絶えられないという批評が多いようです
が、その認識は間違っていないと思います
鴨志田先生はハッキリとお答えになったわけではありませんが、この作品は鴨志田先生の青春であり、我々の青春でもあるゼロ年代(2000年~2009年)のヲタク文学への鴨志田先生なりの愛とリスペクト、そしてアンサーが詰まった作品に仕上がっているんですよ
具体的に言うなれば『AIR』『Kanon』『涼宮ハルヒの憂鬱』『化物語』といった作品群へのオマージュが満載なのです
これらの「パクリだ」と声を荒げるのは簡単なのですが、SFなんだけども既存SFファンからは白い目で見られていたこれらゼロ年代ヲタク文学作品達に、愛と敬意と科学的根拠を用いた解答を提示したのが今作なんですね
つまり『青ブタ』とはゼロ年代ヲタク文学の総決算だということです!
例えば有名人であるが故に周囲に溶け込もうと周りとの関係を断ち、周囲も無視を決め込んでいた末に他人から存在を認知されなくなった桜島麻衣先輩の症状
これは観測する事で存在が確定する“シュレディンガーの猫”で説明が出来、誰にも観測されなくなった麻衣先輩は存在が消滅するのだという展開に広がるのです
これSFかー?って批判もある事でしょうw
でもそれまんま『涼宮ハルヒ』の頃に世間で錯綜していた批評感なんですよねw
歴史は繰り返すw
田村里美さんのキャラデザや高田晃さんの作監もあって画面クオリティは凄く高いです
高田晃さんの顔の内側にまつげを描くと『青ブタ』のキャラっぽくなる、という発見は流石のお仕事ですb
2~3話に一度クライマックスを迎える構成なので結構泣くシーンが頻繁に登場して画面からは目が離せない
6話で何度も通り雨を印象付けた上で泣くシーンに合わせて雨降って→雨上がる、って構成と演出もズルいですねぇ、素晴らしいですねぇ
画面が良く出来ているので音響面の演出は抑え目にしてリアリティを追求した、と岩浪良和監督は仰ってました
会話劇なのでセリフを聴かせようということですね
劇伴なんかも控えめです
例えばパク音と言われる咀嚼音がありますが、キャラが飯を食う時に声優に「はむっ」って言ってもらうアレです
今作では食事シーンが多く出てくるのでリアリティ追求の為にあえてパク音はやらなくていいよ、と岩浪監督は指示したそうです
「はむっ」とか言いながら飯を食う人間は現実にはいませんからね
ところがよく聞くと梓川かえでというキャラだけはこのパク音、わざらしく言ってるんですねーw
な
ぜ
な
ら
、
か
え
で
ち
ゃ
ん
は
、
理
想
の
妹
を
演
じ
て
い
る
か
ら
w
いやー、伏線は張られていたー!
怖い怖いw
そもそも久保ユリカさんがシリアスな芝居をしている時点で察しが着きそうですw
あの久保ユリカの説得力の無い声(笑)でシリアスな役を演っているんですよ!?
つまりソコには意味があるわけです
いやはや恐れ入った;
9話と10話で麻衣先輩とは全くの別人を演じ分ける瀬戸麻沙美さんも凄い
岩浪監督曰く、瀬戸さんと石川界人さんは特に指示しなくてもなんでもこなせて若いのに凄いらしいです
あとは双葉理央の孤独感を出す為にアフレコ現場では種崎敦美さんにわざと声を掛けず、孤立するように仕向けたって話も好きですw
種崎さんが可哀想w
そして妙にしっとりとした劇伴
最初に観始めた時にオシャレだけどなんか引っ掛かるなーというか違和感というか異化効果を感じていました
そしてあのEDテーマ…
裏拍を打っている…!コレはジャズか…!
ってなって背筋ゾクってなりましたわ
fox capture planといえばドラマの劇伴なんかで最近よく目にするようになりましたがアニメを手掛けるのは恐らく今作が初
いやまた凄い人達を連れて来ましたね
個人的に増井監督作品はしっとりとしたEDが多い印象です
『すてプリ』とか『サクラクエスト』とか
さて、完結篇となる6月の新作劇場版が今から楽しみで仕方ない
最近『グリザイア:ファントムトリガー』のクリスとムラサキを足して割ったようなキャラがもしいたら最高なんだけどな~、って思った矢先に観始めた『青ブタ』で双葉理央を発見してしまったので好きが止まりませんw
以上、双葉理央の作ったカレーを食べたいけみかけでしたー
「流石けみかけ、ブタ野郎だね」