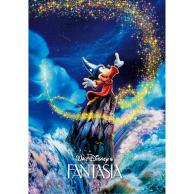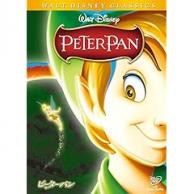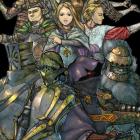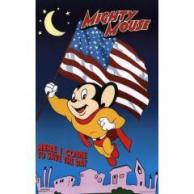前田定満 さんの感想・評価
4.3
クラシック音楽を聴くきっかけに!
□「ファンタジア」とは
ディズニー長編アニメ3作目の作品です。このアニメは一般的なアニメではありません。普通のアニメと違う所はセリフが無く、「音楽(サントラ)が主役」な点です。普通のアニメでは、アニメーションとその内容を盛り上げるために音楽(サントラ)を付けます。しかし「ファンタジア」はそれが逆で、元からあるクラシック音楽にアニメーションを付けています。
製作:ウォルト・ディズニー
総監督:ベン・シャープスティン
編曲.オーケストレーション
レオポルド・ストコフスキー
キャスト
オーケストラ指揮:レオポルド・ストコフスキー
オーケストラ:フィラデルフィア管弦楽団
ミッキーマウス:ウォルト・ディズニー
ナレーター:デームズ・テイラー
制作会社:ウォルト・ディズニー・プロダクション
公開日:1940年11月13日(USA)、1955年9月23日(日本)
上映時間:115分
□各作品内容
{netabare} 「ファンタジア」というタイトルの中で8つの作品に分かれており、作品と作品の間には説明のナレーションが入ります。大きく分けると第一部に4作品と第二部に4作品となります。一部と二部の間には休憩として、楽器の紹介とちょっとしたコーナーが設けられております。
~第1作:「トッカータとフーガ ニ短調」~
作曲:ヨハン・セバスティアン・バッハ
{netabare} 1作目「トッカータとフーガ」はファンタジアの他の曲とは違い、ストーリー性がなく情景を表さない「絶対音楽」という音楽です。なので画も音をアニメーションに表したような抽象的なものです。
実写のオーケストラの映像から始まり、途中からヴァイオリンの弦が動くアニメーションになり、徐々にアニメーションが増えて、最終的に壮大なアニメーションになっていきます。アニメーションと実写の融合作品。まさに芸術作品という感じです。{/netabare}
~第2作:「くるみ割り人形」~
作曲:ピョートル・チャイコフスキー
{netabare} 第2作以降は「絶対音楽」とは真逆のストーリー性や情景を表す「標題音楽」になります。2作目の曲はバレエ組曲です。原曲との大きな違いは曲順です。
・原曲曲順
「第1曲:序曲」、「第2曲:行進曲」
「第3曲:金平糖の踊り」、「第4曲:ロシアの踊り」
「第5曲:アラビアの踊り」、「第6曲:中国の踊り」
「第7曲:葦笛の踊り」、「第8曲:花のワルツ」
・ファンタジア曲順
「第1曲:金平糖の踊り」、「第2曲:中国の踊り」
「第3曲:葦笛の踊り」、「第4曲:アラビアの踊り」
「第5曲:ロシアの踊り」、「第6曲:花のワルツ」
※ファンタジアでは「序曲」と「行進曲」はありません。
この作品にはくるみ割り人形は登場しません。ファンタジアでは妖精や花やキノコや金魚が踊りを披露します。特に「アラビアの踊り」の金魚は色っぽいです。「花のワルツ」のストコフスキーの曲の締め方に注目です。{/netabare}
~第3作:「魔法使いの弟子」~
作曲:ポール・デュカス
{netabare} これはファンタジアの看板作品です。魔法を覚えたばかりの弟子が解き方も知らずに魔法を使い、最終的に魔法が暴走してしまうという物語です。ファンタジアの作品の中で
はこの作品が実際の音楽のストーリーに最も忠実です。弟子役はミッキーが勤めます。魔法をかけうかれた弟子がうたた寝して夢を見るシーンは有名なシーンです。{/netabare}
~第4作:「春の祭典」~
作曲:イーゴリ・ストラヴィンスキー
{netabare} 元々はロシアのバレエ団のために作曲されたバレエ曲です。しかしながらファンタジアでは別の解釈をして「地球の歴史」をテーマに描かれています。
[一部]
地球誕生からマグマオーシャンを経て地球に海が現れるまでを描いています。時代でいうと先カンブリア時代の冥王代の約46億年前から始生代の始め約40億年前までが描かれています。溶岩が流れる画や海底火山の画は素晴らしく、約80年前の作品とは思えない素晴らしい技術です。
[二部]
生命誕生から恐竜絶滅までを描いています。時代でいうと先カンブリアの真ん中の約35億年前から始生代、原生代、古生代と来て、やっと中生代の恐竜時代です。
恐竜時代の見所はT-REXがステゴサウルスを狩るシーン。恐竜の他にも海の最強爬虫類モササウルスも登場します。しかしその後恐竜は「干ばつ」により絶滅します。現在は「隕石の衝突」とそれによる「環境の変化」が絶滅の要因とされていますが、上映された1940年のあたりでは「干ばつ」が絶滅の要因と考えられていました。恐竜が絶滅したあと再び時代が変わり海が帰ってくるところでお話は終わります。{/netabare}
~幕間~
ここで少々休憩タイムです。この休憩タイムでは楽器紹介を兼ねた、ちょっとしたアニメーションがあります。笑える演出も用意されています。
~第5作:「田園交響曲」~
作曲:ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
{netabare} ファンタジアの曲の中で最も好きな曲が、この「田園交響曲」です。タイトル通り田舎の風景を描いた曲です。
・各楽章タイトル
「1楽章:田舎に着いたときの愉快な感情のめざめ」
「2楽章:小川のほとりの光景」
「3楽章:田舎の人々の楽しいつどい」
「4楽章:雷雨、嵐」
「5楽章:牧人の歌 嵐の後の喜びと感謝の感情」
映画のストーリーは曲のストーリーに近いですが、ファンタジアではこれにギリシャ神話を加えています。なのでキャラクターもペガサス、ケンタウルス、ユニコーン、ゼウスなどが登場します。{/netabare}
~第6作:「時の踊り」~
作曲:アミルカレ・ポンキエッリ
{netabare} 大変楽しい曲です。特に終盤付近から始まるメロディーはノリが良いです。ここではいろいろな動物が登場してバレエを披露します。ダチョウ、カバ、ゾウ。しかしみんな女役。この3種類が可愛く色っぽく見えるのは不思議です。これぞディズニーマジック!中盤以降から男役のワニを交えて盛大に踊りは終わります。{/netabare}
※第7作と第8作は繋がっています。
~第7作:「禿山の一夜」
作曲:モデスト・ムソルグスキー
{netabare} 第7作はホラー作品です。悪霊たちの夜の祭りを描いています。お墓などから出てきた悪霊達が夜の世界で踊り狂います。
しかし悪霊たちの楽しい祭りも終わりを迎えます。朝を迎えるのです。教会の音と共にラストの8作目に続きます。{/netabare}
~第8作「アヴェ・マリア」~
作詞:ウェルター・スコット
作曲:フランツ・シューベルト
ソプラノソロ:ジュリエッタ・ノービス
{netabare} 第8作は第7作で踊り狂った悪霊たちの魂を巡礼者達がロウソクの光でしずめていくという演出です。小さいときに観たときはつまらなかったですが、大人になってみると非常に美しいなと思います。そして太陽の光と共に全ての作品が終了します。{/netabare}
全曲について、映像と合わせるために編曲されているので、まんまではありません。カットされている部分があったりなど。
またこの映画の見方として、全作品を通して観ようとするのはやめた方がいいです。作品ごとに分けて観ることをオススメします。{/netabare}
□こんな人にオススメ!
{netabare} まずこの映画の魅力として、芸術性が非常に高いということです。「アニメーションの質の高さ」。まず一つ目の魅力です。アニメーションを楽しみたい方にまずオススメです。約80年前も昔の作品とは思わない映像技術、作画技術をぜひ一度はご覧になるべきだと思います。
クラシック音楽が好きな方にはもちろんですが、クラシック音楽を聴いたことがない人にオススメです。ファンタジアは音楽をアニメーションによって面白くした映画なので、観たあとに「この曲印象に残ったな」と思ったら、ぜひ原曲を聴いてみていただくといいと思います。{/netabare}
□音楽の解釈
{netabare} 私は音楽を専門にやっているわけではありませんが、(聴き手側として)一つ思うことがあります。聴き手側として大切なことは「聴いてどう感じたか」ということだと思います。「悲しい曲だなあ」とか「楽しい曲だなあ」とか「聴いてて、こんな情景が浮かんだ」などなど。思い描く風景、抱く感情は人それぞれだと思うわけです。もちろんプロの演奏家が意識してるのは「作曲家の心境」を考えて演奏するわけですが。
この映画を観る前にファンタジアの音楽を聴いた人にとって、自分の思ってた風景と違うと思う方がいるかもしれません。「春の祭典」は違いすぎますが…。あるいは専門家からみたら実際の作曲家のイメージじゃないと思われるかもしれません。(特に第4作は…)。それにより不快感を持つ方もいらっしゃると思います。(ストラヴィンスキーは怒ったようです…)。それでも是非、広い心で「こんな解釈もあるのか!」と観ていただければと思います。事実、映画の冒頭でナレーターがこの映画について「専門家の解釈ではないところが良い。」と言っています。
私はファンタジアに倣ってクラシックのコンサートに行くと、帰り道によくその曲から感じる風景をスケッチブックに描いて楽しんでいます。もちろん風景を想像しやすいようにある程度予習しますが。{/netabare}